伝えたいもの 2004.3.15 |
| 今年のお雛様には特別の思い入れがある。 故に、雛祭りを過ぎても片付ける気になれず、弥 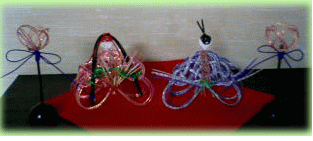 生の間は飾っておこうと思っている。 生の間は飾っておこうと思っている。私が初めて手がけた「水引のお雛様」を。 如月の声を聞く頃、水引の良さを伝えたいと81歳の先生が、函館のご自宅で無料講習会を開かれた。 水引には結ぶ、編む、巻くという技があるが、先生の御手から生み出される水引のアートはまさに神業。 私はすぐさま美しい造詣の妙味に心を奪われてしまった。 先生は、私のように不器用で呑み込みの悪い生徒にも優しく、根気強く、とてもパワフル! 打ち明けると、半分以上は見かねた先生に作っていただいたものである。 単に水引と言えば、贈答用の金封や結納に使われる水引細工を連想されるだろう。 一方、水引幕というのもある。 葬儀の式場に張られる白や紋入りのもの、またはお祭りの山車の三方(側面と後ろ)に下げる幕であったり、土俵の上の吊り屋根に張り巡らされているのも水引き幕である。 国技である相撲の歴史は平安の昔に遡り、相撲節会の時代から陰陽五行に従って、しきたりを大切に守り続けている。 「水は不浄の塵を払い、その元は清浄なり。」 つまり水引は葬儀や祭礼の場を清めるのと同時に、神仏が宿る場所との結界の役目を果たしていたと言える。 水引が日本に伝えられたのは飛鳥時代遣隋使の小野妹子が帰朝した607年。 隋からの返礼の品には、航海の無事を祈ると同時に真心のこもった贈り物であることを表す意味で、紅白に染め分けられた麻紐が結ばれていたという。 やがて日本でも、宮中への献上品に紅白の麻紐を結ぶことが慣例となり、平安時代には「水引」と呼ばれようになる。 一般的に使われるようになったのは、髪や髷を結わえたり、綴り紐やお茶の袋の口を縛るなどの用途に用いられた「 今や現代人に最も身近にある水引と言えば、慶弔に使う金包であるが、小笠原流礼法によると間違った使い方が指摘されている。 水引の本数にも陰と陽があり、本来は用途によって正しく用いられねばならない。 吉の場合、水引の色は赤、紅白、金銀。本数は9本、7本、5本と奇数。 凶の折色は白、銀。本数は二本、四本の偶数。 従って現在市販されている凶事用の白黒の水引は五本でふさわしくないものである。 本物の水引ならまだ一本減らすことも出来るが、水引が絵に描いた餅のように印刷され、香典の字までもが機械的な活字でべったり印刷されているのを見ると、人の心など伝わるものだろうかと考えさせられてしまう。 元結は断髪令以前、日本髪を結っていた大正の頃まではどこの家の鏡台の引出しにも日常的にあったことから、 「凶の折、亡くなられて直ぐには元結を二本用いる。水引の白よりひそやかで悲しみの色が感じられる。」と礼法は伝授する。「ひそやか」と言う言葉に日本人のゆかしき美徳が象徴されているような気がする。(NO21へ続く) |
